とても面白く、興味深いお話しだった。とても惹きつける話し方で後半が楽しみです
今では現代最強のマーケターと言われる森岡毅氏ですが、ご自身の就職活動時代から今まで失敗ももちろん色々あるわけで、就活中の大学生や、建築業の男性、フリーになったばかりのアナウンサーなどいろいろなジャンルからの出演者の質問に自らの失敗談・経験談と共に話してくれるのでとても分かりやすかったし、共感させられた。納得でした。
そして最初に彼が言っていたこと「今まで気をつけてきたことでもあるが、どんな悩みもその人にとっては大切な思いがあるがゆえの悩みであり、そこを理解した上で何か参考になることを伝えられればと思う。とはいえ私の考えは私の考えであって、誰かに強要したり、絶対こうだと言えるものは何一つないが、私が腹の底で信じていることを伝えようと思っています」
素晴らしいじゃないですか!
森岡氏の思うキャリアにおける成功法は3つ
1、自分の特徴の理解
2、環境の選択
3、特徴を武器に変えて磨いていく努力。ひたすら縦に積んでいく
キャリアの定数・変数で言うならば、この3点以外のものは自分で頑張ってもエネルギー浪費するだけでコントロールできないキャリアの定数、上の3点は自分でコントロールできるキャリアの変数。こちらに集中して頑張ると人生うまく回り出す
彼の就活時の失敗談が面白かった。失敗を失敗で終わらせるのではなく、それを良い方向に転換していくことを考えるということ
『転ぶなら前向きに転ぶ。ダメならそれで良いじゃん!』
失敗してもいい、とにかく前向きにやってそれが大切な経験に変わる
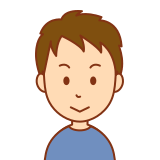
二つの進路をどちらを選べば良いか、進むべきか分からない。
目指したい憧れの人(ロールモデル)はいるのだけど、自分が心地よいと思うジャンルがちょっと違う。どうすればいいのか?
良い経験はどちらの領域の方が多かったか?それを考えると大体見えてくる
森岡氏の経験上は得てして憧れる相手って自分にないものを持っている → だから憧れる
キャリアが定まっていない段階で「自分がこう言う人間になっていたらいいなぁ」と想像する
ここに大きな矛盾が生じて「なりたい自分」と「なれる自分」が一致しない
その結果、多くの人が人生に対してやる気が削がれてしまう
それはなぜか?
最大の要因は、自分の特徴を自分で認められない
「ああ言う人になりたい」と憧れる
「憧れの人の特徴」= 「自分の特徴」 → 一致していたら幸せ
「憧れの人の特徴」≠ 「自分の特徴」 → ほとんどの場合はこちら
自分の特徴を認めなければ成功が遠のく。それは森岡氏が自分の特徴を活かせなかった若き日の苦い経験から気づいた
成功している人はその人の特徴がはまっている。このことはどの分野においても例外がない
自分の特徴がはまっているところが競争が激しかったとしても、その中で自分の特徴をどう磨いていくかを考える方が勝算は高いと思う
ああいう人になりたいというロールモデルを見つけなさいと言われるが、最も必要なロールモデルは自分の特徴に似た人がどう成功したのかというロールモデル
成功者はその人の特徴が生きる環境を選択できたから特徴の芽が出て花が咲いた
自分の特徴が強みになるか弱み(弱点)になるかは環境によって変わる。
ある環境では弱みとなるかもしれないが、ある環境になると強みになる。
例えば、自分の特徴 弱み:空気が読めない
しかしこれも環境が変われば周囲を気にせず自己主張できるという強みに変わる
なので、自分の特徴を活かせる環境で勝負するのが大切!
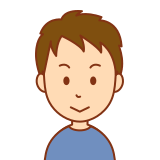
今就活中で、内定4つもらったものの会社、業界がバラバラで自分のやりたいことがわからない為、どの業界に進めばいいか分からない。どう選んだらいいの?
内定4つももらえていいじゃないか。贅沢な悩みだと思われがちだが、これは本当に辛い大きな悩み。
なぜなら、自分が今から選ぶものがどういう結果を産むか分からないのに、選ぶタイミングだけがくる。
じゃあ、どうすればいいか?答えとして2つ言えることがある
まず、、、
① 正解はたくさんある。どの会社を選んでもたいてい選択肢は正解。ただし、「数ある選択肢の中から大吉を引こう」と思うことがあまり良くない。大吉を引こうとするのではなく、たくさんある吉、小吉、それか中吉を引けばいい。それを大吉にするのは入った後の自分次第。なので、どこに入っても正解にすることはできる。
たくさん正解の選択肢があると思うことが重要で、その中にはもちろん失敗の選択肢もある。それは何かというと、自分に合っていない職能(職種)にハマること。それ以外は全部正解
② 会社を選ぶのではなく自分に合った自分の特徴に合致した職能(職種)を選ぶ。
職能(職種)をどういう方向に進めるか、進めていきたいか、それからその職能(職種)を磨ける場所としてどこが適切かという順番で考えていく
業界・会社で選ばず自分の特徴を知り、それが活きて強みとなる職能(職種)を選ぶ。→ それが森岡流キャリア戦略の勝ち筋
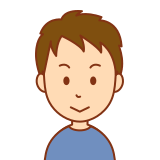
自分が〇〇をしたいというのはどうやって見つかればいいのか?自分の適性となるのか?
適性をどう知るか、自分の特徴・適性がわかる方法は、、、
自分の強みを知るには動詞で物事を考える 〜することが好き
なるほど!と思いました
同志の中に特徴・強みのヒントが隠れている
例えば、「サッカーが好き」となると「名詞」になってしまうが、「サッカーの作戦を考えるのが好き」だと動詞となる。できるだけ動詞に変えて考えていく
これは私も実践してみようと思いましたが、
自分がやってみて楽しかった「動詞」を最低50個、重なってしまってもいいのでできれば100個ポストイットに書き出し、『T』、『C』、『L』の3つに分類する
これだけ書きだせば自分自身もわかるよね。自分自身のマーケティングとでもいうのでしょうか
Thinking (考える力)作戦を考える、戦略化タイプ → 考えることが好きな人に向いた職業例として、ファイナンス、コンサルタント、研究職、マーケティング等
Communication (伝える力)人と接する → 人と繋がることが得意な人に向いた職業例として、営業職全般、プロデューサー、広報等
Leadership (人を動かす力・変化を起こす力)〜を成し遂げる → 職業例として、経営者、管理職、プロジェクトマネージャー等
書いた100個を3つに分類し貼って、どこが1番貼ってあるか見た時に自分の傾向が見えてくる。特徴それぞれに向いた職能があるので、これを大体外さなければ大凶を引いたりはしない。中吉以上は引ける
同時に弱点も大体わかるので、弱点が1番重要視される職能(職種)は避けていく。でも、そこに恵まれなかったけど他の特徴を持つ自分だからこそできることがあり、いろいろな人がいて、噛み合って社会は成り立っていく
会社なので、自分の特徴に合わない職能に振り分けられることがあるかもしれないけど、そこでいかに自分の特徴を活かせる場に転換させていくかと考えるのも必要でしょうね。会社となると自分の意志でどうにもならないことはたくさんありますし。ここが最初の
『転ぶなら前向きに転ぶ。ダメならそれで良いじゃん!』
失敗してもいい、とにかく前向きにやってそれが大切な経験に変わる
ということになるのでしょう。
自分の特徴で向いたところを選んでいき、向いた方向の中からやりたいことを選んでいく。一つの正解にはほぼ間違いなくたどり着くはず
、、、だいぶ長くなってしまいました。まだ、子の情報過多の世の中から本当に必要な情報はどのように得ていくか等あるのですが、続きは次にしましょう。できる限り、細かく見たことを書いたつもりではいますが本当は是非見て欲しい。前回の林修先生と森岡氏のインタビューに関してはYouTubeにUPされているのですが、今回のものはされていないんです。されないかなぁ、、、
とりあえず、次回続きUPするので楽しみにしていてくださいね
私も前向きになれた熱血授業でした
À bientôt! ^^

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/28a30d04.1e1c6d7f.28a30d05.02afb152/?me_id=1213310&item_id=19526700&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7829%2F9784478107829_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)


コメント